






仏教壮年会(順教寺)
目標
1.聞法する仏壮の輪を広げる。
1.お仏檀を中心に家庭生活を営む。
1.寺院活動に積極的に参加し、宗門の護持発展に努める。
1.青少年の育成のために、対話のある家庭をつくる。
1.定例勤行及び仏壮行事への積極的な参加に努める。
1.会員の増員に努める。
平成25年度事業計画
毎月第3日曜日 夏季(4月~9月)7時~8時 冬季(10月~3月)8時~9時 定例勤行の励行(全員に案内状を配布)
仏壮だより
毎月1回発行
その他の事業の取り組み
| 年月日 | 曜日 | 開催地 | 開催場所 | 行事名 |
| 25.4.20 | 土 | 河内町 | 順教寺 | 順教寺降誕会前日 会場準備 |
| 25.4.21 | 日 | 〃 | 〃 | 順教寺降誕会 当日お手伝い 参詣役員会 |
| 25.4.21 | 日 | 〃 | 〃 | 順教寺仏教壮年会第14回総会 |
| 25.6 | 広島市 | 広島別院 | 安芸教区仏教壮年会連盟総会・前期研修会 | |
| 25.6. | 安芸教区東部地区仏教壮年会 | |||
| 25.7.13 | 土 | 河内町 | 順教寺 | 第2回ともしびの集い |
| 25.7.21 | 日 | 〃 | 〃 | 順教寺境内・周辺草刈り |
| 25.9 | 賀茂東組南法中仏教壮年会・前期研修会 | |||
| 25.11 | 丸亀市 | 中国・四国仏教壮年大会 | ||
| 25.11.17 | 日 | 河内町 | 順教寺 | 順教寺境内・周辺草刈り |
| 25,11. | 〃 | 〃 | 順教寺報恩講(逮夜席)参詣・お手伝い | |
| 25.11 | 広島市 | 広島別院 | 仏教壮年会連盟単位代表者連絡協議会 | |
| 25.12。14 | 土 | 本郷町 | 広島エアーポートホテル | 賀茂東組南法中仏教壮年会後期研修会・忘年会 |
| 25.12.31 | 火 | 河内町 | 順教寺 | 順教寺除夜会 |
| 26.1.1 | 水 | 〃 | 〃 | 順教寺元旦会 |
| 26.1.15 | 水 | 〃 | 〃 | 御正忌報恩講(逮夜席)参詣・お手伝い |
| 26.1.18 | 〃 | 〃 | 土曜学校(餅つき) | |
| 26.3. | 〃 | 〃 | 順教寺仏教壮年会役員会(次年度総会対応) | |
| 26.3 | 広島市 | 広島別院 | 安芸教区仏教壮年会連盟大会・公開講座 | |
順教寺仏教壮年会組織
順教寺
| 住 職 | 吉川 省慧 |
| 前 住 職 | 吉川 昭丸 |
| 副 住職 | 吉川 隆史 |
顧問及び参与
| 役 職 名 | 氏 名 |
| 顧 問 | 山根 琢磨 宗平 紀彦 |
| 参 与 | 盛田 明 平賀 闊 |
役員
| 役 職 名 | 氏 名 |
| 会 長 | 戸光 正彦 |
| 副 会 長 | 増田 豊實 増田 強 |
| 幹 事 | 宮脇 公司 松仁 忠義 戸光 博治 三好 愛 上本 覚 山内 清水 |
| 事務局(書 記) | 平野 政敏 |
| 事務局(会 計) | 三好 博水 |
| 監 査 役 | 舛田 隆司 細国 敬三 |
親鸞聖人関東ご旧跡参拝と東京スカイツリー ~親鸞聖人関東布教800年~
期 日 平成26年11月4日(火)~11月7日(金)
日 程
| 1 | 11月4日(火) | 広島空港=東京・羽田空港=昼食=下妻・小島の草庵跡=下妻・光明寺=結城・称名寺=稲田・西念寺(泊) |
| 2 | 11月5日(水) | 稲田・西念寺=玉日廟参拝=板敷山・大覚寺=笠間・光照寺=昼食=高田専修寺=願入寺=大洗(泊) |
| 3 | 11月6日(木) | 大洗=河和田・報仏寺=飯富・真仏寺=水戸偕楽園(散策と昼食)=河合・枕石寺=西山荘=東京(泊) |
| 4 | 11月7日(金) | 東京=築地本願寺参拝=都内観光(東京スカイツリー、浅草雷門など散策と昼食=東京・羽田空港=広島空港 |
旅 費 お一人様98,000円
お申し込み 8月20日(水)までにご返信下さい。 順教寺 電話082-437-1012
第14回崇徳教社講演会 あんたもわたしも安芸門徒デー
日 時 7月14日(月)13:30~16:30 (開場13:00)
場 所 本願寺広島別院 本堂 (広島市中区寺町1-19 TEL082-231-0302)
講 題 「浄土真宗と愛」
講 師 中央仏教学院 院長 白川 晴顕 先生
参加費 1,000円(当日券のみ)
ふれあいアワー
第1部 広島音楽高校生徒による楽器演奏
第2部 崇徳高校グリークラブ生徒による演奏
主催 真宗崇徳教社 共催 崇徳学園 後援 中国新聞社/本願寺広島別院/浄土真宗本願寺派安芸教区/見真学園/進徳学園
お問い合わせは崇徳教社事務局まで TEL082-238-3838
第3回順教寺仏教壮年会法座 ともしびの集い
日 時 7月12日(土)18:00~21:00
場 所 順教寺本堂
懇話会 庭(雨天の場合は庫裡)
講 題 「いくつになってもほとけの子」
講 師 志摩 寛仁 師(大和町和木見正寺住職)
会 費 2,000円
どなたでもお参り下さい。懇話会では酒を出します。お帰りの車が必要な方はお申しつけ下さい。 順教寺TEL437-1012 戸光TEL437-0609
役員会(仏教壮年会法座)
日 時 6月26日(木) 19:00~
場 所 順教寺 庫裡
審議事項
第3回順教寺仏教壮年会法座について
第34回順教寺門信徒役員研修会
日 時 平成26年6月19日
場 所 姫路 (善教寺・亀山本徳寺)
不動山 善教寺 浄土真宗 本願寺派
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 入り口へのアプローチ | 御本尊 | 大勢至菩薩・観世音菩薩 | 聖徳太子像 | ご住職 | 鳥かご鐘楼 |
ご住職(結城思聞)の法話
キーワード:ノーマライゼェーション、ジ・チャレンジド、集団的自衛権、戦争のない平和な社会の構築
亀山本徳寺
 |
 |
 |
 |
 |
||
| 立派な門 | 格式ある塀 | 本堂 | 本堂の内部 | 法話をされた方 |
法話
蓮如上人の生い立ち、石山本願寺と信長の戦い、その際の村上水軍の役割等、本徳寺が蓮如上人を開基として開創され播州の真宗勢力の最大拠点になる経緯
弱きもの人間 欲深きものにんげん 偽り多きものにんげん そして人間のわたし みつを
親鸞聖人降誕会
4月19日(土)
9:30 降誕会 お勤め
10:00 第10回順教寺寄席 笑福亭仁智 師匠
11:30 初参式 3才以下のお子様の初参式です。仏婦幹事さんか順教寺へお申しこみ下さい。
12:00 敬老会 75才以上の方に楽しく会食していただく場です。仏婦幹事さんへお申し込み下さい。
14:00 土曜学校開始式
14:30 人形劇 呉「あひる座」 子猫はどうやって鳴き方を覚えたか くじ引き
15:45 終了
上記のように、宗祖親鸞聖人のご誕生日をお祝いして、法要をお勤めすると共に、いろいろな行事を行います。ご家族、ご近所、お誘い合わせお参り下さい。 合掌
順教寺 順教寺入野真宗婦人会 順教寺仏教壮年会
| 降誕会のタイムスケジュール | ||||||||
| 行程表 | ||||||||
| 月日 | 会場 | 行事の行程 | 仏壮会の取り組み | |||||
| 時間 | 行程 | 時間 | 取り組み内容 | 要員 | ||||
| 4/18(金) | 本堂庫裏 | 14:00~ | 会場設営・高座本堂へ移動・くじ引き準備 | 5名以上 | ||||
| 8:30 | 赤飯の持ち帰り(竹原) | |||||||
| 本堂 | 8:30 | 仏教壮年会集合 | ||||||
| 本堂 | 9:30 | お勤め | 9:06 | 笑福亭仁智師匠迎え (入野駅) | ||||
| 本堂 | 9:50 | 高座設置 | ||||||
| 本堂 | 10:00~ 11:00 | 笑福亭仁智師匠による寄席 | ||||||
| 本堂 | 11:00 | 会場整理 | ||||||
| 本堂 | 11:30~ 12:00 | 初参式 | ||||||
| 11:30 | 笑福亭仁智師匠送り | |||||||
| 4/19(土) | 庫裏の玄関の間 | 11:30 | 初参式列席者を対象としてくじ引き・景品交換 | 10名以上 | ||||
| 本堂 | 12:00 | 会場整理 | ||||||
| 庫裏 | 12:00~ 13:30 | 敬老会 | ||||||
| 庫裏の玄関の間 | 14:00 | 敬老会列席者を対象としてくじ引き・景品交換 | ||||||
| 庫裏 | 13:50 | 会場整理 | ||||||
| 本堂 | 14:00~ 14:30 | 土曜学校開校式 | ||||||
| 本堂 | 14:30~ 15:40 | 人形劇 | ||||||
| 庫裏の玄関の間 | 15:40 | 参詣者全体を対象としてくじ引き・景品交換 | ||||||
| *赤飯持ち帰りは、山内清水氏 笑福亭仁智師匠送迎は、書記 平野政敏が担当 | ||||||||
平成26年仏壮総会
平成26年4月13日(日)19:00~順教寺において、総会を開催します。
副住職さんの法話
御門徒さんのお宅にお参りさせていただくと、ときどきロウソクについての質問がありますので、今回は蝋燭(ロウソク)のお話をさせていただきます。
まず、ロウソクに火を点じて仏さまを荘厳(しょうごん)することを“点燭(てんしょく)”といいます。仏前に灯火を献じるのはインドから伝わっており、ロウソクを用いるようになったのは、中国の宋の時代で、日本には室町時代の初めに伝わったとみられます。
ロウソクの灯火は、仏さまの智慧を表しており、お寺の法要やお仏壇の荘厳には欠かせないものの一つです。平常のお勤めには白色のロウソクを用いることがほとんどですが、法要の主旨によっては白色以外のロウソクを用いることもありますので、紹介いたします。
① 白蝋(はくろう) ・・・ 一般の法要に用いる。日常の勤行や月命日など。
② 朱蝋(しゅろう)赤色 ・・・ 報恩講・永代経の法要や初参式・落慶法要。
年忌の法事(ただし七回忌以後)
③ 金蝋(きんろう) ・・・ 慶讃法要(きょうさんほうよう)や仏前結婚式など、喜びの大きい法要・儀式。
④ 銀蝋(ぎんろう) ・・・ 葬儀・追悼法要・三回忌までの年忌の法事など、
悲しみの大きい法要・儀式。
以上の4種類があります。
このように人生の様々な場面に応じて、ロウソクは使い分けられています。
※ご法事は、故人を偲ぶ法要ですが、同時に私が仏法にあわせていただくご縁でもあります。七回忌以降は、故人を縁として仏法にあわせていただく事に重きをおくという意味から、朱蝋(赤色)を用います。
平成25年度仏教壮年会役員会
平成26年3月16日(日)9:00~役員会を開催します。平成26年4月開催されます、総会への事前検討。
春彼岸法座
3月10日(月)昼席 午後1時半 3月11日(火)朝席 午前9時半、昼席 午後1時半
講師 本願寺派布教師 吉崎哲真先生
副住職さんの法話
お彼岸にあたって
先日、ある御門徒さんのお宅でのご法事のことです。ご自宅で一周忌をお勤めしたあと、少し離れたお墓に移動して納骨をいたしました。お骨を納骨するとき、亡くなられた方の奥様やお集まりになったご親戚の方々が、悲しみのあまり涙を流して別れを惜しんでおられました。
お墓の前でお勤めした後、少しお話をさせていただきました。
私たちが今、となえています「南無阿弥陀仏」は、単なる六つの文字ではないと常々、聞かせていただいております。阿弥陀さまが「南無阿弥陀仏」のお名号の姿となって、私の口から出てきてくださっているのです。「南無阿弥陀仏」と私の口で称えてはおりますが、それは仏さま〝そのもの〟であると聞かせていただいております。私の口を通しておそばに来てくださっているのです。ですから、先立たれたご主人様もきっとお浄土で仏さまとなっておられるのですから、どこか遠いところにいってしまったのではなく、私が「南無阿弥陀仏」と称えるなかに、出遇わせていただくことができるのです。
いつもおそばに来てくださっていますよ。
と、お話させていただきました。
大切な人と別れる苦しみや悲しみは、とても深く、簡単に受け入れられないということをあらためて教えられた気がいたします。自分自身の〝死〟への不安と同じように、〝大切なあの人〟はどこへいったのか、ということも切実な思いがあるということを知らされました。
3月はお彼岸があります。
先にお浄土にまいられた大切なあの人に思いをよせ、仏法を聞かせていただきたいと思います。
平成26年2月22日(土)9:00~土曜学校
あんなにしてやったのに「のに」がつくと ぐちがでる (みつを)
平成26年2月16日(日) 8:00~順教寺において勤行。
前住職さんの法話 恩について 1.先祖の恩 2.自然の恩 3.社会への恩 4.仏恩 がある。目に見えない支えによって生かされている。
副住職さんの法話
はやいもので、年が明けてもうひと月が経ちました。
去る1月15日・16日、順教寺では御正忌(宗祖 親鸞聖人の御命日)をお勤めさせていただきました。御正忌はわれわれ浄土真宗にとっては、最も大切な法要であります。
さて、2月には涅槃会(ねはんえ)という日があります。2月15日はお釈迦さまがお亡くなりになられた日で、この日を涅槃会といいます。順教寺では涅槃会の法要は行ってはおりませんが、仏教徒である私たちは知っておきたい大事な日であります。
お釈迦様はクシナガラ(インド北東部)で、80才のご生涯を終えられました。35才でさとりの道が完成し、仏陀(目覚めた者)となられてからお亡くなりになるまで、万人が救われる法を説きつづけられました。
「 すべてのものは移り変わる。 たゆまず努力せよ 」
これがお釈迦様の最後の言葉であったと伝えられています。
最後まで無常をさとること、修行に励むことを説かれました。移り変わる無常の世界だからこそ、努力し続けることが大事であるとお教えくださいます。何事も簡単に投げ出してしまう自分を振り返り、改めて気を引き締めることであります。
※お釈迦様はクシナガラでサーラの双樹(沙羅双樹)の下で、頭を北、顔を西、右脇を下にして、横になられました。そして、お亡くなりになったとき、サーラの樹が白く変化したと伝えられています。現在、わたしたちが葬儀の際には、白い紙で作った『紙華(しか)』をお供するのは、お釈迦様の最後の様子に由来するものです。
土曜学校「餅つき」
土曜学校の子供達と餅つきを行います。会場のセット、餅米蒸し、餅つき指導、餅丸め、会食、片付け等です。冬のひと時を、地域の子供達と共に楽しみましょう。
日 時:平成26年 1月18日(土)8:30集合~11:30片付け・解散
*餅の材料や搗くための道具は準備してあります。
 |
 |
 |
 |
多数の参加者があり、楽しく、にぎやかに餅つきが行われました。子供達には、大変良い経験になりました。ご父兄の皆様ありがとうございました。
紙上法話
〝一年の計は元旦にあり〟 念仏もうさるべし
去る12月31日から1月1日にかけて、順教寺では除夜会・元旦会を勤修いたしました。仏教壮年会会員の皆さまには、早くから焚き火や照明等のご準備をいただき、誠にありがとうございました。おかげさまでたくさんの方々と賑やかに新年を迎えることができ、心より感謝申し上げます。
新年最初の法話にあたって、蓮如上人(第八代宗主)のお言葉を紹介いたします。
蓮如上人の門弟であった勧修寺村の道徳という人が、元日、蓮如上人のもとへ新年のご挨拶にうかがったところ、上人は、
「道徳はいくつになるぞ、道徳念仏もうさるべし。・・・」
とおっしゃられました。
年頭の挨拶はふつう「明けましておめでとうございます」というのが一般的でありますが、蓮如上人は、「念仏申しなさい」と新年の挨拶にお念仏を勧められました。
一年間という長い月日には、私の身の上にいろんなことが起こります。楽しいことやうれしいこともあれば、どんな災難に遭遇するやもしれません。しかし、お念仏の法にあわせていただくと、どんなことがこの身に起きようとも、安心して生き、安心して死んでいける道が開かれているのですと、一年の最初にお念仏を勧められています。
年頭の心改まる時に、あらためて大事に聞かせていただきたいお言葉であります。
本年もよろしくお願い申し上げます。
御正忌法要
平成26年1月15日(水) 夜席 午後7時30分より。1月16日(木) 昼席 午後1時30分より
親鸞聖人が往生されたのは1月16日です。わたしたちに、お念仏の教えを広め仏になる道を明らかにして下さった聖人のご恩徳を偲び執行させて頂く法要です。どうぞ御誘い合わせてお参り下さい。
除夜会・元旦会 お手伝いのお願い!
除夜会・元旦会の法座が行われますので、たくさんのお方のお詣りとお手伝いをお願いします。
12月31日(大晦日) 23:00 集合・焚き火 : ろうそくの設置・点火(灯篭・石段)
23:30 記帳場での記帳案内、ぜんざいのもち焼き
1月 1日(元旦会) 1:30 かたずけ
除夜会、元旦会のお勤めに続いて、ぜんざいの接待、ジャンケンゲームなどがあります。ご家族もお誘い下さい。
賀茂東組仏壮連盟研修会
平成25年12月18日(水) 正覚寺(福富町)において、開催されます。順教寺仏壮から3名が出席します。
副住職さんの法話(12月紙上法話)
去る11月27日・28日・29日、順教寺報恩講法要を勤めさせていただきました。
遠近各地たくさんの門信徒の方々が順教寺の本堂にお参りくださいましたこと、本当に有難いことであると感謝いたしております。
報恩講は宗祖親鸞聖人のお徳を偲んで勤められる法要でありますから、わたくしたちにとっては最も大切な法要であります。私が今「南無阿弥陀仏」とお念仏を申し、阿弥陀如来さまのお救いに出遇うことができたのは、ひとえに親鸞聖人ご生涯かけての求道があってのことと、有難くお勤めさせていただきました。
今年も残すところわずかとなってまいりました。振り返ってみますと、いろんなことがありました。親しい人との別れ、新しい出会い、うれしかったこと、悲しかったこと。ときには泣いたり、怒ったり、笑ったり。それが生きているということなのでしょう。そのどんな場面にも、「南無阿弥陀仏」となって一緒に歩んでくださる仏さまがいらっしゃったことを、この報恩講で思い出したことであります。私が忘れていても、決して忘れてくださらない阿弥陀如来さまの御心に、今年も遇わせていただきました。来年もまた皆さまとご一緒に遇わせていただきたいと思います。
来年もよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
南法中仏教壮年会後期研修会
平成25年12月14日(土)17:00~広島エアーポートホテルにおいて、研修会・忘年会が開催されます。
安芸教区仏壮連盟寺院仏壮代表者連絡協議会
平成25年11月10日(日)本願寺広島別院において、講話・意見交換会が開催されました。
順教寺報恩講法要ご案内
浄土真宗の門信徒として、親鸞聖人のご恩を偲ぶ報恩講法要にぜひ、お参り下さるようご案内いたします。
順教寺報恩講
11月27日(水)夜席 19:30~
28日(木)朝席 9:30~
昼席 13:30~
入野真宗婦人会報恩講
11月29日(金) 朝席 9:30~
講師 若林 眞人 師(大阪市淀川区 光照寺)
聖典・念珠・式章をご持参下さい。お斎は、28日・29日の11時半~13時の間にお着き下さい。28日、竹原地区・安芸津地区には、マイクロバスを運航します。
順教寺平成26年3月までの法座案内
除夜会・元旦会 12月31日(火) 23時45分
1月 1日(水) 0時30分
ぜんざいの接待やジャンケンゲームがあります。
御正忌 1月15日(水) 夜席19時30分
16日(木) 昼席13時30分
15日は親鸞聖人のご生涯を描いた御絵伝の解説と「御伝鈔」の拝読があります。16日正午から13時まで聖人ゆかりのあずき粥を接待していただきます。
順教寺入野真宗婦人会定例法座 2月6日(木) 昼席13時30分 講師 加藤 広慶 師(本願寺派布教使:乃美 教得寺)
会員以外の方も、どなたでもお参り下さい。
春彼岸法座 3月10日(月) 昼席
11日(火) 朝席 昼席 講師 吉崎 哲真(本願寺派布教使:佐伯区 西法寺)
朝席は9時30分、昼席は13時30分です。
副住職さんの紙上法話(11月)
「少欲知足」の教え ~足ることを知る~
去る10月24日、順教寺役員研修旅行に行かせていただきました。この度は、広島市内にある本願寺広島別院と教専寺さまに参拝させていただき、午後は中国新聞社ちゅーぴーパークを見学いたしました。台風の影響で雨が降る中、47名の役員・門信徒の方々がご参加くださいました。
広島別院参拝の後、西区田方にある教専寺さまで故選一法(こせん いっぽう)先生の御法話を聞かせていただきました。先生は、長きにわたって『アミダの森』(砂漠化がすすむ内モンゴル地区に緑を)という活動を、中心になって支えてこられました。この活動は、人間の幸せのためだけでなく、動物や植物も共に生きていく『共生』ということを目指して取り組まれてきました。もっと豊かに、もっと便利で快適にと、人間の都合で豊かな自然や大地を破壊してきたから、少しでも命を育む大地に〝いのち〟をお返ししようと、砂漠に苗木を植える緑化活動であります。
先生はお話の中で、「少欲知足」という仏教の教えが、いまとても大事なことであるとお話くださいました。「足る」ことを知らなければ、人間の欲は果てしなく続きます。もっと、もっと、という生き方では、いつまでたっても幸せにはなれません。いま、すでに多くの恵みによって生かされていることに目を向け、今の有り難さに気づかせていただくことが、全ての命が共に生きる世界への第一歩であると聞かせていただきました。
第33回順教寺門信徒役員研修会との合同研修会
平成25年10月24日(木)8:00~バス2台に分乗して、広島別院、教専寺(西区田方)、中国新聞ちゅーピーパークにおいて研修を行いました。
広島別院
広島別院の由来 本願寺広島別院は、その昔、長祿3年(1459)武田山のふもとに建立され、竜原山仏護寺と称し、当時は天台宗であったが、同寺第二世円誓は本願寺蓮如上人に帰依し、明応5年浄土真宗に改宗した。第三世超順の頃、毛利元就は仏護寺を護持し、天正十八年(1590)に輝元が広島城を築いた時、仏護寺を広島小河内町へ移転、次いで慶長十四年(1609)年、藩主・福島正則が、現在の地に移転させ寺町とした。明治三十五年十一月には、広島別院仏護寺と称し、更に明治四十一年四月に本願寺広島別院と改称して今日に及んでいる。昭和二十年八月六日原爆により焼失し、安芸門徒の懇念を結集して、昭和三十九年十月に現在の本堂が完成し、さらに再建後30年目の平成二十三年四月には大ホール等を備えた安芸門徒会館が完成し、ひろく安芸門徒の信仰の道場としてその偉容を保っている。
参考 安芸教区とは? 浄土真宗本願寺派では、全国を31の教区、533の組に分けています。広島県西部の地域を安芸教区と呼び、25の組があります。教区内には現在550ヶ寺ほどの一般寺院があります。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
上の写真で左から、歓迎の掲示、本堂、安芸門徒会館共命ホール、安芸門徒会館安穏の間、原爆で焼失する前の別院、順教寺前住職 吉川昭丸氏贈呈による別院の水墨画、親鸞聖人御銅像
教専寺(西区田方)
西区草津本町の本坊と田方の支坊があり、今回は支坊にお世話になりました。支坊は、昭和63年、団地開教の為広島市佐伯区美鈴が丘団地が出来ると同時に、団地への道の途中に開創。多目的ホールを備えた本堂、鐘楼、庫裏、墓地が境内にあり、聞法道場として活動。教専寺前住職の故選一法師は、中国内モンゴル地区への植林事業「アミダの森 協力隊活動」を長年にわたり支えてこられました。すべてのいのち輝けという阿弥陀様の願いに応え、「ごめんなさい、ありがとう」と、いのちの源である大地に、いのちをかえす砂漠緑化の活動です。現在はその志を受け継ぐ中国の方々に事業を託しておられます。
教専寺支坊の由来 50年前西部開発事業に伴って、埋め立てに必要な土を山を削り充当していた。(現美鈴ヶ丘団地の場所) その山には、狸やイノシシが生息していたが、人間の欲望の為に生活圏が侵害された。自然保護や災害の防護、環境問題、生物多様性の観点からも人間はやりすぎである。人間という動物が、動物たちの生息場所を奪い、尊いいのちを亡くしている。海に目をやると埋め立てにより、多くの貝や生物が死滅した。これらの思いは、すべての命を助ける概念観に基ずいている。昭和52年草津の門徒さんから説教寺を懇願され、おりしも漁師さんには、埋め立てによる漁業権に係る補償金も入ったことから、人望・人徳のある総代長さんのご尽力により、昭和62年本堂が出来た。一万戸の美鈴が丘団地への門徒勧誘活動を行っている。当時、環境問題がクローズアップ、おりしも京都では、環境問題に係る京都議定書が公布、砂漠に木を植える縁を得て、植林事業に傾注する。
参考 環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニア人女性、ワンガリ・マータイさん。マータイさんが、2005年の来日の際に感銘を受けたのが「もったいない」という日本語でした。
これらのことから、人の生きる指針として、前住職は一つの示唆をされました。ワレ・唯・足るを・知る京都・龍安寺の茶室の入り口の置かれている「つくばい」が、吾・唯・足・知という四文字をデザイン化したもので出来ています。水戸黄門さんが寄贈されたものと伝えられています。「足るを知る」という仏様の教えが表されているのです。大無量寿経にお念仏のお徳を「小欲知足」「和顔愛語」としめされています。念仏生活をする私たちは、「欲を少なく・足るを知る」の実践を心がけたいものです。
前住職からのお願い いろいろ物議をかもしているが、「はだしのげん」を読んでほしい。戦争は絶対ダメ!念仏は世界平和に通ずる。
所感 前住職の積極的な行動力に感銘を受け、ただ敬服する。
 |
 |
 |
 |
 |
ちゅーピーパーク見学(中国新聞印刷工場)
大型の輪転機がずらり!超高速のスピード印刷!世界のトップクラスの設備!
中国新聞が刷り上がるまで 最高速度で1時間に18万部、1秒に50部を印刷する世界トップクラスの能力を持つ工場です。
印刷用の版づくり 中国新聞本社から紙面の元となるデータが送られてきたら、アルミ版に焼き付けます。多い日は1日に1000枚作ります。
輪転機に版を取り付け ページの順番やカラーページを確認しながら、輪転機に取り付けます。
用紙をセット 紙庫から取り出された巻きとり紙は、コンピューターの指令を受けた運搬装置(AGV)によって、輪転機まで運ばれ、自動で取り付けられます。紙の重さは、1.4トン!
印刷開始 朝刊55万部を約3時間で刷り上げます。
運転は、コンピューター管理 この大きな輪転機は、コンピューターで管理していますが、色や見当合わせの微調整は人間の力が必要。スタップは常にモニターに目を光らせています。
紙面を折る 刷り上がった紙面を折り曲げたたむのも機械の仕事。高速で正確に折りたたんで行きます。
紙面チェック ページ順にセットされて出てくる新聞紙を、定期的に抜き取りチェックします。スタップはチェック機能装置さえも通過した印刷の小さなズレや汚れも見逃しません。
つり下げて運搬 刷り上がった新聞は、1部ずつ「キャリア」という機械でつり上げられて、頭の上を移動し、発送エリアに運ばれます。
行先ごとに梱包 カウンタースタッカーで部数を数え、バーコード付きの宛名紙が添えられ、フィルム包装とバンドをかけて梱包完了。
コンベアーでトラックへ バーコードで配送先が管理されているので、仕分け作業も自動。梱包された新聞は、コンベヤーに載って流れ、トラックの2台へ直行。
トラックホームから出発 約500点ある中国新聞販売所へ向かって出発します。配送トラックの全車の走行距離は1日で約6300キロ。
工場の中はこうらっている!地上4階建ての工場の中には、最新の機器が並びスムースに作業ができる工夫も、いろいろなところに見られる
とても大きな輪転機 輪転機は印刷機械の一種で、新聞や雑誌など大量に印刷するものに使われる。
ここの温度は快適だ 工場全体が温度24度、湿度55%に保たれている。紙は環境によってシワになったり乾燥したりするから、温度管理はとても大切です。
新聞印刷には何色使うの? 青・赤・黄・黒色のインキを使っている。この順に一色ずつ刷り重ねていくことで、カラーの印刷になる。
印刷ズレはどうやって見つけるの? 新聞の下端にある4色のレジスターマーク(色玉)を使って確認するよ。一直線・等間隔に並んでいたら正常。自動見当装置が確認する。
1日に100本を使用 工場には、巻きとり紙の倉庫が2つあります。多い日には1日100本の巻きとり紙を使い、ほとんど毎日補充されます。1本の重さは約1.4トン。およそ4日分を保存しています。
エコなインキで印刷 大豆油を使用したエコインキは、環境にも、働く人にも読む人にも優しいインキ。高速で印刷しても霧状になりにくい粘り気のあるインキです。
機械を止めずに紙を補充 1代の輪転機に3本の巻きとり紙が付いていて、1本ずつ使われます。紙が残り少なくなると予備の紙が動き始め、自動で紙継ぎをします。
世界で最も早い輪転機を備えた中国新聞の工場で新聞作りを身近に感じた。機械・技術・歴史的な変遷、情報収集から編集・いくつものチェック機能を経て印刷、配送の説明を受ける。
今月の標語 助けて下されよというにあらず、助かってくれよとある仰せに従うばかりなり 順教寺の掲示より
平成25年10月26日(土)広島別院において、こども報恩講の開催。
平成25年10月20日(日)8:00~9:00順教寺において、仏教壮年会 朝の集い(勤行)
副住職さんの「仏壮だより」の紙上法話(10月)
近頃、異常気象という言葉を耳にすることが多くなったと思います。今年の夏も全国的に35度を超える猛暑が何日も続き、また局地的大雨や竜巻の発生など、自然がもたらす災害で多くの方々が被害に遭われ、なかには命を落とされる方もたくさんおられました。
異常気象とは、数十年に一度の現象をいうそうです。しかし〝こう毎年のように異常気象が起こると、もはや異常ではない〟という記事を見たことがあります。
〝異常〟とは、国語辞典によると「普通またはいつもと違っていること」とありました。
仏教の教えに出遇ったものは、常々この世は〝無常〟であるとお聞かせいただいております。〝常が無い〟とは、〝普通〟とか〝いつも〟というもの自体が、そもそも存在しませんよ、この世はいつ何時、何が起こっても不思議ではないですよ、そういう世界を生きているのですよ、とお教えくださっています。この度は逃れましたが、いつか逃れられない〝無常の波〟が必ずやってくることに耳を傾け、いつ、どこで終わったとしても、迎えてくださる世界にいま出遇っていることを確かめたことであります。
南法中5ヶ寺(立栄寺・長照寺・安楽寺・元浄寺・西立寺・順教寺)主催のもとに、9月14日(土)午後7:00~21:40順教寺において、開催された。長照寺ご住職の勤行に始まり、順教寺副住職さんの法話がありました。その内容は、仏檀は江戸時代末期に広く普及し、金仏檀は本願寺の縮小を模している。お仏檀に向かう心構えについても、定まった形はないと言及されながらも、亡くなられた人との接点の機能、先祖を敬う・苦しみ・楽しみの報告や語らい等多様性がある。
向かって、中央に仏像・絵像・名号(南無阿弥陀仏)、右に親鸞聖人、左に蓮如上人の絵像が掲げてあり、南無阿弥陀仏の信心を持って、私の元に伝えられた弥陀の教えを喜び、有り難さを受け止めることも大事で、往生即成は浄土真宗の特徴とのことでした。
グループでの話し合いでは、「お仏檀にお参りするとき、先祖や家族の事をお祈りしますが、それでも良いのですか」をテーマに二班に分かれて話し合いました。多くの意見として、先祖供養、感謝、奉仕、生かされている気持ち、祈り、会話、心のよりどころ、報告、家内安全等でした。
最後は、立栄寺の前住職さんの挨拶で終わりました。その中で、仏檀に向かうと「心が落ち着く」安らぎが得られる。ご本尊から光明が放たれる。これが聴聞にも通じる。篁の郷
 |
 |
 |
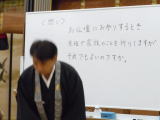 |
 |
順教寺門信徒役員研修会との合同研修会(ご案内)
平成25年10月24日(木)8:00~役員研修会が執り行われます。研修先は、広島別院・教専寺・チューピーパーク(中国新聞)です。有意義な研修とともに、他の役員さん達との交流等楽しい一日を過ごしてみませんか。希望者は、戸光・平野まで。
賀茂東組南法中仏教壮年会・後期研修会
平成25年12月14日(土)17:00~エアーポートホテルで開催する予定です。
浄土真宗本願寺派順教寺仏教壮年会会則
(名称)
第1条 この会は、浄土真宗本願寺派順教寺仏教壮年会(以下、「順教寺仏壮」という。)という。
(目的)
第2条 この会は、順教寺化教区に所属する門信徒たる仏教壮年の結集を図り、宗派の基幹運動(門信徒会運動・同朋運動)を推進すると共に、宗門の護持発展を図ることを目的として組織する。
また、浄土真宗本願寺派安芸教区仏教壮年会(以下、「教区連盟」という。)と、情報・活動の交流を図り活動推進に努め、浄土真宗本願寺派仏教壮年会連盟(以下、「仏壮連盟」という。)の発展に資する。
(事務所の所在地)
第3条 この会の事務所を、東広島市河内町入野2745番地 順教寺内に置く。
(加盟登録)
第4条 この会は、仏壮連盟及び教区連盟に加盟登録する。
(構成)
第5条 この会の構成は、順教寺化教区に所属する門信徒たる仏教壮年で30歳以上のものを会員として構成する。
ただし、連盟から役員の選出依頼があった場合には、役員会において65歳以下の会員の中から互選し、住職が任命する。
(会費)
第6条 会員は、この会の運営に必要な経費を、会費として負担する。ただし、特別の行事その他重要な事柄に関する経費の負担は、会員の意見を聞いて決定する。
(役員)
第7条 この会に、次の役員及び連盟から選出依頼のあった役員(以下、「依頼役員」という。)を置く。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 幹事 若干名
4 監査役 2名
5 事務局 2名(書記:1名 会計:1名)
6 依頼役員 連盟からの依頼人数
(役員及び依頼役員の任免)
第8条 役員は、順教寺仏壮総会において会員の中から互選し、また、依頼役員は、総会において会員の65歳以下の中から互選し、住職が任免する。
(役員の職務)
第9条 会長は、この会を代表して、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は、会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。
3 幹事は、会長の命を受けて会務を分担し処理する。
4 監査役は、この会の会計業務を監査し、会に報告する。
5 事務局は、書記1名、会計1名で構成し、この会の書記事務・会計事務を処理する。
6 役員は、役員会を組織して、この会の事業を執行し、臨時緊急のある事項について審議・決定する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、その任期が満了後においても、後任者が選任されるまで、その職務を継続する。
3 補欠による役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(顧問及び参与)
第11条 この会に、顧問及び参与若干人を置く。なお、顧問には会長経験者、参与は総代その他協力者を当てる事が望ましい。
2 顧問及び参与は、役員会の議を経て、住職が委嘱する。
3 顧問は、この会の運営に関する重要な事柄について、会長の諮問に応ずる。
4 参与は、この会の目的達成について協力する。
(運営)
第12条 この会の運営に関する重要な事項については、役員会において審議・決議する。
2 役員会の開催は、住職の承諾を得て会長が行う。
3 役員会は、役員の過半数の出席を必要とし、その議事は役員の定数の過半数で決定し、その役員の議決権は、各々平等とする。
4 住職・顧問及び参与は、必要に応じ役員会に出席し、意見を述べることが出来る。ただし、可否の数に加わることはできない。
(総会)
第13条 この会は、総会を毎年1回開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することが出来る。
2 総会は、会員をもって組織する。
3 総会は、住職の承認を得て、会長が招集する。
4 総会の議長は、出席者の互選により決定する。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。ただし、可否同数の場合、議長が決定する。
6 住職、顧問及び参与は、必要に応じ総会に出席し、意見を述べることが出来る。ただし、可否の数に加わることはできない。
(総会の権限)
第14条 総会は、次に掲げる事項について協議・決定する。
1 活動・事業・行事に関すること。
2 予算・決算、その他会計に関すること。
3 会則の変更に関すること。
4 役員の選出に関すること。
5 その他会務に関する重要事項で、会長が必要と認めた事項
(経費)
第15条 この会の運営に必要な経費は、次に掲げる収入をもって当てる。
1 会費
2 強化助成金
3 事業収入
4 寄付金
5 その他の収入
(他の規定)
第16条 会費・弔意細則を別に定める。
(会計年度)
第17条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
1 この会則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この会則の施行の際、現に従前の仏教壮年の結集に関する宗則(昭和54年宗則第2号)、及び、仏教壮年の結集に関する宗則施行条例(
昭和54年宗則第12号)に基づき、仏教壮年会連盟規約のもと加盟登録された仏教壮年会は、連盟に加盟登録されたものとみなされる。
3 この会則の施行日において、この会の現役員は、第10条の規定に関わらず、任期限を平成23年3月31日とする。ただし、連盟に選出している依頼役員は、当該連盟の規約によるものとする。
4 「平成22年4月25日 一部改正」を加える。
会費細則
(金額)
第1条 会費は、1会計年度あたり1,000円とする。
(納入時期)
第2条 会費は、当該年度の総会時の納入を、原則とする。
(助成活動)
第3条 この会の、活動の拡大・発展のため、次の助成を行う。仏教壮年会行事(順教寺の行事は、除く)に参加した場合は、活動助成として1,000円を、また、行事に懇親会が付随し自己負担の場合は、2,000円を助成する。旅費は、実費を支給する。なお、自家用車使用の場合あは、自宅を起点として1㎞当たり、30円を支給する。
附則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
弔意細則
(対象範囲)
第1条 ご逝去された会員を、対象とする。
(金額)
第2条 ご香典として、3,000円をお供えする。なお、ご葬儀当日に「ご香典」としてお供え出来なかった場合には、後日、「ご仏典」としてお供えする。
附則
この細則は、平成22年4月1日~施行する。